こんにちは、投資経験25年のサラリーマン投資家、みつぞうです。
今日は、私がこれまで歩んだ道、これまでの投資遍歴をご紹介したいと思います。
72の法則って何?
令和2年6月現在で、定期預金の利率はいくらぐらいでしょうか?
答えは、1年定期預金で年利0.2%程度です。それも金利に力を入れているネット系の銀行の場合で、一般の都市銀行では0.002%です。
みなさんは、72の法則という言葉を聞いたことがありますか?
お金が2倍になる期間を簡単に計算できる法則で、次の式で表されます。
72 ÷ 金利 ≒ お金が2倍になる期間
先の0.2%の1年定期の場合、資金が2倍になる期間は360年。
都市銀行の0.002%においては、なんと36,000年かかります。
今日は、私が資産運用を始めた90年代の金利やその他の投資環境について、私の事例とともにお話ししてみようと思います。
※この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
高金利のバブル時代
私が資産運用を始めたバブル当時は、6%もの高金利。
資産が12年で2倍になる時代で、「定額貯金」*に預けるために、皆が郵便局に押し寄せ、長い行列ができているのが報じられていました。
* 定額貯金は半年複利で効率が良かったので人気でした。
バブル崩壊から低金利時代へ

その後、バブル崩壊とともに金利は毎年のように引き下げられ、定期預金で1%台、普通預金で0.1%台の低金利時代となりました。
それが現在まで続いているのです。
バブルより前の7%代の時代を知る両親は、当時「昔は10年で2倍になったのに」と嘆いていました。
バブル崩壊後、預金金利が下がるのに応じて、少しでも金利の高い預け先はないかと、割引債や日興のチャンス、MMF、外貨建てMMFなどいろんな金融商品を渡り歩きました。
(当時は債券ベースの、比較的リスクの小さい商品で運用していました)
そして、金利が高めの債券ベースの商品も次第に利率が低くなったり、販売終了したりで、ついに投資信託の購入に至ったのです。
金融ビッグバン〜新しい投資の時代へ。そしてITバブル崩壊
ちょうどその頃、金融ビッグバンの流れの中で様々なインターネット銀行ができたり、銀行で投資信託が買えるようになって、投資信託ブームでした。
当時の投資信託には愛称が付けられていて、私が購入した投信には、「グローイングエンジェル」とか「シナプス」とかといったものがありました。
今思えば、全くの素人で、買い方も信託報酬の高さもわかっていなかったので、信託報酬が2〜3%の投信を10万円とか20万円とかまとめて購入したりしました。
また、投信ブームで様々な鳴り物入りの投資信託が発売されました。
私が飛びついたのは「日本戦略株ファンド」です。
純資産額が1兆円を超える大型ファンドでしたが、購入すると間も無くITバブルが崩壊して、評価額は半分以下になり長期塩漬けを余儀なくされました。

スポンサーリンク
投信積み立てとインデックスファンドへの目覚め
その後、投信積み立てというものを知り、毎月1万円を数銘柄に積み立てました(今では信じられませんが、当時は、最低購入金額が1万円だったのです!!)
月々購入する投資信託の中には、個人投資家の長期投資を呼びかける、当時としては先進的な「さわかみファンド」も含まれていました。
購入手数料は無料、信託報酬が1%というのも当時としては良心的でした。
私は、その理念に惚れ「このファンドに掛けてみよう」と思いました。
それから、投資関連のサイトやブログで勉強する中で、インデックスファンドが良いらしいことを知り、世界株と世界債権のインデックスファンドをそれぞれ積み立てることにしました。
長くなったので、本日はここまで。近々続きをアップしますね。
最後までお読みいただきありがとうございました!!
#積み立て貯蓄 #さわかみファンド #投資信託 #インデックス投資 #長期投資













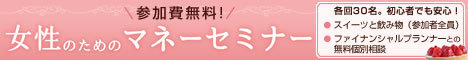

コメント お気づきの点がありましたら、お気軽にお書きください。